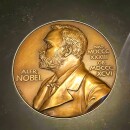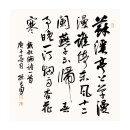なぜ台湾は日本のようにノーベル賞が取れないのか―台湾メディア
拡大
9日、台湾メディア・中時新聞網は、「どうして台湾は日本のようにノーベル賞受賞者を輩出できないのか」と題した台北商業大学元学長の張瑞雄氏によるコラム記事を掲載した。
2025年10月9日、台湾メディア・中時新聞網は、「どうして台湾は日本のようにノーベル賞受賞者を輩出できないのか」と題した台北商業大学元学長の張瑞雄(ジャン・ルイシオン)氏によるコラム記事を掲載した。
張氏はまず、今年のノーベル生理学・医学賞では「制御性T細胞」により大阪大学の坂口志文特任教授が、化学賞では「金属有機構造体の開発」により京都大高等研究院の北川進特別教授がそれぞれ受賞者の1人に名を連ねたことについて、「なぜ台湾の中から受賞者が出ないのか」という疑問を呼び起こすとし、「単に運が悪いで済ませることなく、長期的な制度・文化・学術生態の深層的な相互作用を振り返る必要がある」とした。
そして、日本のノーベル賞受賞は偶然ではなく、戦後からの制度的支援と長期的な研究文化の蓄積によるものだと指摘。制度面では、教育制度や研究機関、資金配分、産学連携など多方面にわたる政策が、高リスクかつ長期的な探究を可能にしてきたほか、理化学研究所や学術振興会、大学の研究センターが産業界と連携してきたことで、基礎研究と応用研究が並行した発展を実現したのだと論じた。
また、日本の研究者は博士課程やポスドク段階で欧米のトップ研究室で研さんを積み、国際的な科学ネットワークと深くつながっているとし、国際的な可視性と交流密度が、成果の認知度を高めているとも解説した。さらに、ノーベル賞級の成果は引用数の多い少数の論文に集中しており、日本は安定した資源と人材の継承により、影響力のある論文を継続的に生み出しているとの見解も示した。
一方で、台湾については経済規模が比較的小さく、政府や企業による基礎研究への投資は限られているため、数年にわたる高リスクの研究を支えるには資源が不足していると指摘。ノーベル賞級の成果を生み出す中核的な研究拠点の形成も難しく、若手研究者が既存の枠組みを超えて大胆な研究を始めるリスクが大きすぎるとしたほか、限定的な資源と文化的な問題によって、失敗が許される長期的かつ試行錯誤を伴う研究を続けることが困難だとも論じている。
張氏は、台湾の現状を打破するためには「偶然に頼るのではなく、政策・資源・評価・協力体制・文化のすべてにおいて同時に変革を起こす必要がある」と論じ、制度面で研究者に対する信頼と柔軟性を高めることが必要だとした。長期的かつ高リスクの研究を支援する基金の設立や、短期的な業績圧力の緩和を進めると同時に、世界レベルの研究センターや旗艦研究室を構築して資源を先進分野に集中させ、国際的なトップチームとの長期的な協力、国際学術誌での露出強化、研究者の国際活動への参加促進などで台湾学術界の国際的な地位を高めなければならないと提言した。(編集・翻訳/川尻)
関連記事
「日本はノーベル賞の数でリードも科学技術では中国に大きく後れ」=中国企業関係者の主張にネット賛否
Record China
2025/10/9
日本がまたまたノーベル賞受賞!われわれは何に注目すべきか?―中国メディア
Record China
2025/10/9
日本人がまたノーベル賞、今年2個目=中国ネット称賛「本当にすごい」「敬服する」
Record China
2025/10/9
日本人がまたノーベル賞受賞、中国との「差」はどこに?―中国メディア
Record China
2025/10/8
ノーベル生理学・医学賞に坂口志文氏=韓国ネット「うらやましい」「誇らしい隣国」
Record Korea
2025/10/7
日本人がまたノーベル賞受賞、中国ネット感嘆「やっぱりすごい」「30年を失ったんじゃ…」
Record China
2025/10/7