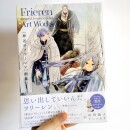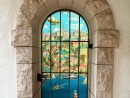少子化日本の軍事大国化ありえず、中韓は?=話題の書「日本 老いと成熟の平和」を読んで
拡大
安全保障関係者の間で話題になっているという「日本 老いと成熟の平和」を読んだ。写真は東京。
安全保障関係者の間で話題になっているという「日本 老いと成熟の平和」(トム・フォン・リ著、2025年みすず書房。英語の原著は21年刊)を読んだ。東アジア情勢の緊迫化などを背景に、一部で日本の軍事大国化を予測ないし期待する声が上がっているが、少子化が進み、かつ国民の平和志向の強い日本ではそうした事態はありえないとする内容だ。果たしてその論旨に説得力はあるのだろうか。そして、近年は日本以上に少子化が加速している中国や韓国はどうなのだろうか。
人口減と平和志向が歯止めに
同書の著者はベトナム系アメリカ人。年齢は不詳だが、写真や経歴から見て、40代の気鋭の研究者と見た。2005年に留学生として初めて来日して以来、20数回日本を訪れ、広島などで総計2年半を過ごし、この間に多数の政治家などにインタビューしたというから、相当の日本通だ。なにより、奥さんは絵里花さんという日本女性で、彼女が「原稿を読み、問題が起こる前に修正し…常識の視点からのチェックを提供してくれた」(序文)という。そのためか、外国人が日本について書いた文章を読む際にしばしば感じる違和感はほとんどなかった。
著者の主張は、222ページの「日本国民にとっては、高齢化と人口減少、そして非軍事主義の規範がある中で、国家の軍事化を支持する理由はほとんどない」という一文に集約できる。ここで言う「非軍事主義の規範」とは、日本社会に根付いた強い平和的傾向、と言い換えることもできるだろう。
高齢化と人口減少は、定数割れという形で既に自衛隊に影響を及ぼしている。先に、陸海空3自衛隊が毎年持ち回りで開いてきた陸自の観閲式、海自の観艦式、空自の航空観閲式が今後は中止されることが決まったが、その背景には深刻な人手不足があると報じられた(8月4日朝日新聞)。24年に生まれた日本人の子どもは過去最少の68万人にとどまり、1年間で日本人が90万人減るなど、少子高齢化と人口減少は一段と加速している。装備を高度化・省力化したとしても、一定数の若者が毎年入隊しなければ自衛隊の組織は回らないわけで、要員の確保は今後一段と難しくなるとみられる。
人口減少のほか、防衛産業の力不足や基地・施設の未整備も軍事大国化の阻害要因になる。防衛産業について言えば、三菱重工業や川崎重工業のような主要メーカーでも、防衛省との契約で得ている売り上げは総収入の1割未満。軍事関連の事業なしでも生き残ることができるため、「競争力を持とうと真剣になることはない」という。
著者によると、広島、長崎の原爆資料館を筆頭に、日本には世界最多の76の平和博物館があり、児童生徒の多くは就学中に一度は博物館を訪れ、それが非軍事主義の継承につながる。また、被爆地の反核運動を中心に、全国でさまざまな平和団体が活動している。その背景には、戦争放棄をうたった平和憲法がある。人口減少や防衛産業の力不足などハード面の理由に加え、戦後の日本社会に根付いた平和志向というソフト面の要因が軍事大国化の歯止めとなっているというわけだ。
安全保障環境は変化したが…
ここで気になるのが、この本の原著が出版されたのが4年前という点だ。その後、世界でも日本国内でも、安全保障を巡りさまざまな動きがあった。ロシアのウクライナ侵攻は、国境を変更してはならないという国際社会のルールを国連安全保障理事会の常任理事国が平気で踏みにじった暴挙であり、中国による台湾侵攻を連想させる効果もあった。イスラエルは諸外国からの批判も意に介さずにガザで民間人の殺戮を繰り返し、ヨルダン川西岸で違法な入植を続けている。米国ではトランプ第2期政権が発足し、自国が作った戦後の国際秩序を自ら掘り崩している。
国内では、ハト派と言われた岸田文雄政権が新たな国家安全保障戦略を閣議決定するとともに防衛費増額の方針を打ち出した。今年の参議院選挙では、「核武装は安上がり」と主張する候補を含む極右と呼ばれる政党が躍進した。一方で、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が24年のノーベル平和賞を受賞し、日本の反核平和運動が国際的にも評価された。力不足を指摘された防衛作業は、英国、イタリアと次世代戦闘機の共同開発に着手したほか、オーストラリア海軍が三菱重工製の最新型護衛艦の採用を決めるなど、ここにきて前向きの動きが出始めた。
このような変化はあったが、著者が重視する人口減少と、国民の平和志向は変わらない。私の意見を言えば、著者の見立てに大筋では賛成であり、この2つの要因が日本の軍事大国化を抑制し、予見しうる将来、既に表明された以上の軍拡は実現しないと考える。ただ、米国が同盟関係の見直しに動いたり、周辺国が極端に挑発的な動きに出たりした場合、世論がどう反応するかは見通しにくいが…。
東アジアの軍拡を抑制?
少子化に悩んでいるのは日本だけではない。23年の東アジア諸国の出生率を見ると、日本1.20、韓国0.72、中国1.00、台湾は0.87と、いずれも深刻な出生数の減少に直面しており、将来的な国力へのマイナスの影響が懸念されている。詳細は不明だが、北朝鮮も少子化傾向にあると言われる。日本以外の各国は、今のところ軍の採用問題は徴兵制で解決しているし、社会に日本のような平和志向があるわけでもない。とはいえ、若者が大幅に減少した後もこれまで通りの徴兵を続けていては、他の分野への悪影響は無視できなくなるだろう。
同書は、中国や韓国などの出生率低下に触れたうえで、「東アジアは、軍事への多額の投資というコースから転じて、その分の資源を、移民制度の整備や、社会における女性の地位向上に振り向けることを今一度考えるべきだろう」と指摘、これら各国でも人口減少が軍事費増加の制約要因になりうるとの見方を示唆している。少子化と人口減少はマイナスの影響ばかりが注目されるが、この地域の軍拡に歯止めを掛ける効果があるのか。注視していきたい。
■筆者プロフィール:長田浩一
1979年時事通信社入社。チューリヒ、フランクフルト特派員、経済部長などを歴任。現在は文章を寄稿したり、地元自治体の市民大学で講師を務めたりの毎日。趣味はサッカー観戦、60歳で始めたジャズピアノ。中国との縁は深くはないが、初めて足を踏み入れた外国の地は北京空港でした。
関連記事
韓国軍の規模が6年で20%減少、原因に少子化―中国メディア
Record Korea
2025/8/11
ミャンマーが労働目的での男性の出国を禁止、背景に戦況悪化か―仏メディア
Record ASEAN
2024/5/7
ジェンダー格差116位の日本が「韓国から学べ」と言われる理由=韓国ネット「韓国は男を冷遇」
Record Korea
2022/7/18
中国の軍艦がドイツ機にレーザー照準、いったい何があったのか?―独メディア
Record China
2025/7/10
マスク氏の日本に関する大胆予言が現実に?最新データに震える―台湾メディア
Record China
2025/6/6
日本で「隠れ教育費」が論争に―中国メディア
Record China
2025/2/23