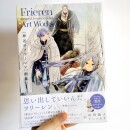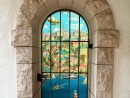日本のトイレットペーパーの薄さに隠されたこだわり―在中国日本大使館
拡大
在中国日本大使館の公式ウェイボーアカウントは28日、「日本のトイレットペーパーの薄さに隠されたこだわり」に関する中国語の記事を投稿した。
在中国日本大使館の公式微博(ウェイボー)アカウントは28日、「日本のトイレットペーパーの薄さに隠されたこだわり」に関する中国語の記事を投稿した。
記事によると、初めて日本を訪れた人の多くが「なぜ日本のトイレットペーパーはあんなに薄いのか」と不思議に思う。経済が発展し、品質を重視する日本が、なぜトイレットペーパーで倹約するのかと疑問に思う人もいるかもしれない。それは本当にコストを抑えるためだけなのか。実はこの「薄さ」は、単に倹約やユーザー体験の軽視ではなく、機能性や環境保護、文化など多くの側面を考慮した上で形成された、一見小さいが非常に独特な日本の生活論理なのだ。日本のトイレットペーパーは一般にパルプ紙ではなく再生紙を使用している。再生紙への移行は、純粋に経済的な理由からではなく、日本の資源的制約や環境意識の高さ、社会的な合意の高まりに起因している。高い森林被覆率を持ちながらも輸入木材に依存している島国である日本は、持続可能な資源利用に関する厳格なガイドラインを定めている。都市人口が多く、公共インフラが整備されていることも相まって、トイレットペーパーのような日用品でさえ環境保護の範疇に含まれる。日本製トイレットペーパーの利点は、水に素早く溶け、分解しやすいことにある。これは特にトイレの排水システムにおいて重要だ。排水管が細く、水圧が不安定な古い建物では、トイレットペーパーが厚すぎると詰まりやすく、メンテナンスコストの増加につながる可能性がある。したがって、機能的な観点においては、日本製トイレットペーパーの薄さは、システムの安全性と持続可能性を考慮した結果であり、妥協案と言える。薄さ自体が、間接的に人々に節約を促している。これは日本のライフスタイル管理に対するきめ細やかなアプローチの証だ。
記事によると、日本の「薄いトイレットペーパー哲学」は、環境保護やシステムの機能性への配慮に加え、独特の美学とライフスタイルも反映している。日本の美意識は、軽やかさと抑制を体現し、シンプルさや自然さ、節度、人工的な要素の排除を追求する傾向にある。この哲学は建築や芸術だけでなく、日常生活のあらゆる側面に反映されている。包装材から食器のデザイン、コンビニエンスストアの食品の盛り付けからトイレの細部に至るまで、実用性と使いやすさが重視されている。トイレットペーパーの薄さは、脆さの象徴ではなく、むしろ環境や用途にふさわしい、より適切な感覚なのだ。そこには、隠された哲学的な論理があるのかもしれない。トイレットペーパーは厚くなくてもよいという現実を受け入れると、人々は機能性や清潔さ、安全性を評価することへと焦点を移していくことになる。この変化は、物質的な所有物への抑制だけでなく、資源への敬意と社会システムへの思いやりを示すものでもある。
記事によると、日本のトイレットペーパーは薄すぎて使い心地が悪いと批判する人もいる。特に厚手の紙に慣れている外国人観光客にとっては、カルチャーショックを受けるかもしれない。しかし、こうした不快感は、文化の違いが些細なことに表れることを改めて認識させてくれる。国がどんなトイレットペーパーを選ぶかは、資源管理へのアプローチや公共性と私的性の捉え方、個人の利便性とシステムの効率性のバランスを反映している。日本のトイレットペーパーはなぜあんなに薄いのか。最も快適ではないかもしれませんが、おそらく最も合理的と言える。それは、環境意識や公共責任、機能的論理、美学を一枚の紙の上に統合した知恵だ。私たちは、それを使用している時には必ずしもその深遠な意味を理解できないかもしれないが、よく考えてみると、この生活の細部の中に、「いかに生きるか」という民族の問いに対する深遠な答えが隠されていることに気づく。(翻訳・編集/柳川)
関連記事
韓国大統領の分身の術、トランプ氏を喜ばせた後に習近平氏を招けるか―香港メディア
Record Korea
2025/8/29
プーチン氏に金正恩氏、トランプ氏が会いたい人が皆、北京に―独メディア
Record China
2025/8/29
日本のサービスの質が下がった?中国ネットで議論「確かに」「以前が良すぎただけ」
Record China
2025/8/29
「日本の“冷たさ”が大好き」との主張に中国ネット「同感」「中国は文明社会の基礎がない」
Record China
2025/8/29
米国、カナダ、ドイツからボリビアまで、各国の政治家はレアアースのことで忙しい―仏メディア
Record China
2025/8/29
韓国ドラマ「暴君のシェフ」で漢字のミス=韓国ネット「漢字学ぶべき」、中国ネット「『世』では?」
Record Korea
2025/8/28