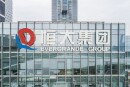中国の人気飲料チェーン「奈雪」の脱日本化進む=新英語名が波紋、遠のくNAYUKI時代
拡大
人気茶系飲料チェーン「奈雪的茶」が米国市場進出を機に英語名称を「Naishow」に変更し、話題になっている。
(1 / 5 枚)
「NAYUKI」から「NAIXUE」を経て「Naisnow」へ。ブランドの熟成と捉えるべきか、それとも戦略の曲がり角と見るべきか。人気茶系飲料チェーン「奈雪的茶」が米国市場進出を機に英語名称を「Naishow」に変更し、話題になっている。雪の結晶をかたどった新デザインにも要注目だ。
【その他の写真】
「脱日本化」のトレンド
「奈雪的茶(ナイシュエ)」は2015年創業の中国発の新式茶系飲料チェーンで、都市部を中心に強固なブランド認知を得ている。フルーツティーとパンを組み合わせたメニューなどで人気を得て成長し、21年に香港証券取引所への上場を果たしたが、24年は9億1900万元(約183億8000万円)の損益を計上し、市場の競争激化が伺える。
こうした中、同ブランドが英語名表記を「Naisnow」に変更し、話題になっている。同ブランドは22年に創業から使用してきた日本語風の「奈雪の茶」を中国語表記の「奈雪的茶」に変更し、読み方も日本語の「ナユキ(NAYUKI)」から中国語ピンインに基づく「ナイシュエ(NAIXUE)」に切り替えた経緯がある。当時、中国国産ブランドの人気が高まる「国潮」の下で広がる「去日本(脱日本化、日本的な特徴の除去)」のトレンドに沿った措置として受け止められた。

「Nai」という響きは適切?
しかし、「Naisnow」という英語名称はいまひとつネット上の反応が芳しくない。音やつづりがしっくりしないと感じたネットユーザーが少なくなさそうだ。日本人目線からしても、「Nai」という音は否定的な語感を持つ。英語圏でも“No”や“Not I”といったネガテイブな響きを連想させる恐れもあるかもしれない。
そもそも、3年前の「脱日本化」の過程で、かわいらしかった「の」を取り去り、「的」に置き換える措置を取ったのは適切だったのだろうか。人によっては読む順序が分からず、「雪茶奈的」と誤認してしまう可能性も否定できない。ブランドメッセージの伝達において混乱を招くリスクは看過できないだろう。

「Snow」を採用した背景は?
また、「Naisnow」という語尾に含まれる「Snow」は、ブランドの清涼感やピュアな雰囲気を表現しようとする試みと理解されるが、日本の老舗乳業メーカー「雪印(Snow Brand)」をほうふつさせるのが気になるところだ。雪の結晶を模したロゴデザインは雪印ロゴミルクなどで海外市場でもおなじみのシンボルとなっている。
両者のデザインにそれほど類似性は感じられない。すると、むしろ奈雪が意識したのは同じ中国国内の茶系ブランド「蜜雪冰城(MIXUE)」だろうか。あえて英語のネーミングにしたのは、「脱日本化」のみならず、多店舗展開で先行するMIXUEに対する牽制の意図も潜んでいるのかもしれない。
成功と失敗から学ぶネーミング
ブランド名は発音、意味、記憶への残りやすさに加え、他ブランドとの類似性を避ける工夫が必要だが、自国市場と海外市場とでそれぞれ異なる名称を使う例もある。抖音(Douyin)が「TikTok」、拼多多が「Temu」、小紅書が「RED」などとしているのは、中国国内と海外とでブランド名を区別して市場展開した成功事例として挙げられるだろう。
一方、「茶顔悦色」が英語名を「Sexy Tea」とアピールしたことが物議を醸したように、文化的誤解や炎上リスクをはらんだ命名も後を絶たない。日本の「カルピス」が英語圏で「Calpico(カルピコ)」という名称でブランド展開しているのはよく知られることだが、グローバル市場における言葉の選び方は慎重を要する。
「気」と「氣」──漢字の訴求力
「元気森林」についても触れておこう。同ブランドは前述した「脱日本化」の社会トレンドを受けて、20年以降に商品パッケージの「気」を中国簡体字の「气」へと変更したが、ECサイトを見たところ、台湾市場では依然として日本語漢字である「気」を使用している。あえて日本イメージを持たせようという戦略なのか、あるいは国・地域ごとに異なる感性への対応かは明言されていない。
そういえば台資企業「元祖食品」は、日本語の音に由来する「Ganso」という表記を中国本土で維持しているのも印象的だ。日本風イメージをむしろ積極的に活用する姿勢と見ることができ、奈雪や元気森林とは対照的なアプローチとなっている。

問われる言葉の設計力
もう一つ補足しておきたいのは、日本では旧体字である「氣」が「気」へと簡略化された歴史にはさまざまな推察が存在することだ。継続する文化の分断と見なす見解さえ存在する。そういう事情はさておいても、台湾市場ではいっそのこと現地で使われる繁体字の「氣」を使う方が好ましかったのではないかとの印象を抱く。

「気」と「氣」、あるいは「NAYUKI」と「Naisnow」。そんなブランド表記の相違点や変化には、さまざまな哲学がにじむ。あるときは経営てこ入れの旗印としての役目を担うこともあれば、あるときは消費者との関係性を再設計する行為として受け止められることもある。それゆえブランド名の刷新は発音や表記、消費者の印象、商標リスクまでを見据えた「言葉の設計力」が大きく問われているといえよう。今後の「奈雪―Naisnow」の市場展開に注目が集まる。(提供/邦人NAVI微信公衆号<WeChat公式アカウント>)

関連記事
「日本式ラベル」外す動き目立つ中国企業、自国ブランドの人気高まり反映
Record China
2023/1/1
「奈雪の茶」がロゴ変更、日本要素捨て「国潮」強調―中国メディア
Record China
2022/11/29
中国にあふれる日本風商品=中国メディア「日本の文字を使わなければ勝てないのか」
Record China
2022/1/22
日本人「中国の商品にひらがなの『の』がよく使われるのはなぜ」、中国人「俺たちも疑問に思ってた」
Record China
2022/1/18
張博恒の日本での人気が中国にバレる
Record China
2024/8/7
タイで行われた韓国インスタント麺販促イベントが日本風に、抗議受け撤去=韓国ネット「すばらしい対応」
Record ASEAN
2024/6/11