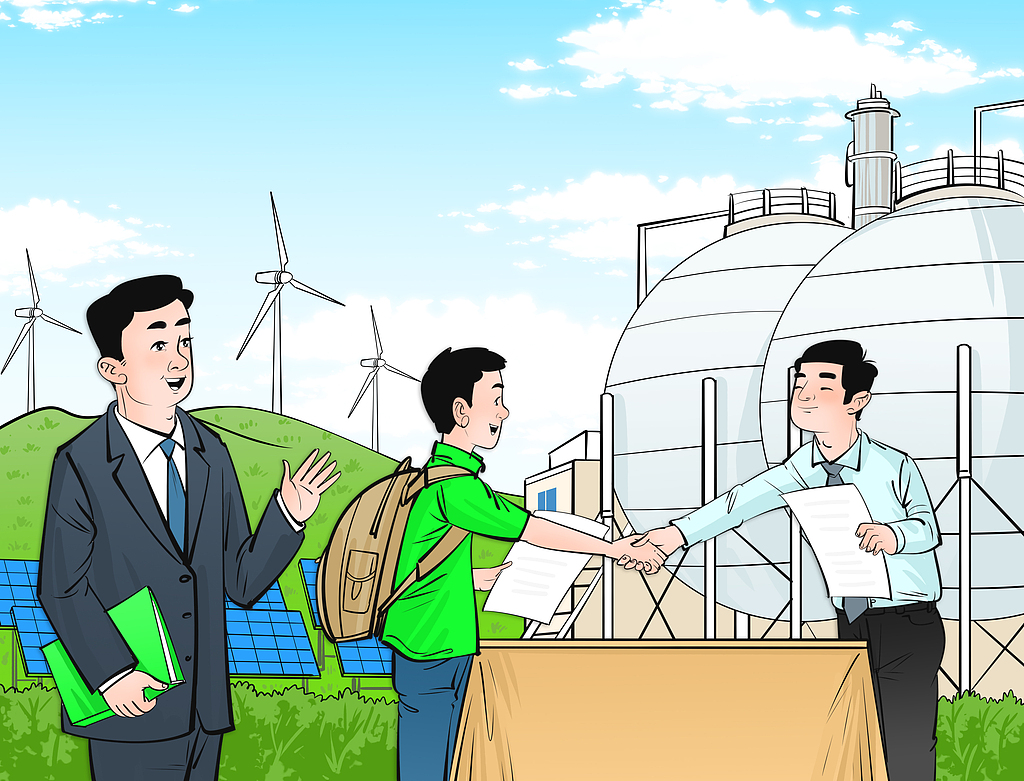ファーストフードが中小都市進出 利益・課題が共存
拡大
中国の基準で考えれば、山東省中部にある人口70万人の鄒平県は発達した地域ではない。山西省太原市のマクドナルドの前を行き交う人々。(撮影・張雲)
中国の基準で考えれば、山東省中部にある人口70万人の鄒平県は発達した地域ではない。同県の賑やかな大通りには、国際的なブランドの店はほとんど並んでいない。だがファーストフードブランドのケンタッキーは、同県に目を付けた。県内にある2店舗には、食事を取る家族連れやデート中のカップルが大勢やって来るという。英国紙「フィナンシャル・タイムズ」のサイトが伝えた。
英調査会社ユーロモニター・インターナショナルのデータによると、中国ファーストフード市場における営業収入の伸びを回復させるため、ケンタッキーとマクドナルドは一日1店舗という猛スピードで店舗網を拡大し、その多くが中小都市にあるという。
報道によれば、2013年以降、消費者が健康志向の高まりによってファーストフードへの興味がなくなり、それが原因でケンタッキーもマクドナルドも中国での営業収入が減少した。日本の大和証券のアナリストは、「今年の新店舗オープンで米ヤム・ブランズ(ケンタッキーを運営する親会社)の中国での営業収入は約1億8千万ドル(1ドルは約113.5円)増加し、この数字は営業収入の増加額予測の約半分にあたる。13年以降、ヤム・ブランズの中国営業収入は前年並みか減少を続け、昨年の営業収入は67億ドルだった」と述べる。
まもなくヤム・ブランズ中国法人の最高経営責任者(CEO)に就任するジョーイ・ワット氏は、「弊社は中国1100都市で業務を展開するが、現在検討中のところがあと900カ所ほどある。このことは中国の発展の潜在力を物語る」と話す。
報道によると、ヤム・ブランズは中国でケンタッキー5300店舗を運営し、この数字はマクドナルドの中国店舗の2倍にあたる。今後5年以内に、マクドナルドは中国で新たに2千店舗をオープンする予定だ。マクドナルドは、「2020年をめどに、中小都市のマクドナルド店舗を45%にする」という。
これらのファーストフードチェーン企業は中小都市の賃金上昇というチャンスを利用する構えだ。英メディアによれば、米コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーがまとめたデータをみると、こうした都市の消費者は大都市の消費者と同じく西洋のファーストフードチェーンにしょっちゅう来店し、消費金額は大都市よりも多いという。
報道では、思いがけない困難もあるとしている。コンサルティン会社ボストン・コンサルティング・グループのアナリストのビンセント・ルイさんは、「上海の100店舗をうまく管理できる従業員を雇うことは簡単だが、さまざまな都市に散らばる100店舗を管理することは簡単ではない。遠隔地に新店舗を開設すれば、より多くのマネージャーを雇い入れなければならなくなり、コストがより高くつく。これと同時に、マクドナルドやケンタッキーのようなファーストフードブランドは中小都市でも高い競争力をもち、価格競争の圧力が高い。ケンタッキーに似たところのある中国発ファーストフードのディコスは中国で2千店舗以上を展開し、そのほとんどが小都市にある。長期的なリスクがどこにあるかといえば、中小都市の消費者も大都市の消費者と同様、いつかファーストフードに飽きる日が来るかもしれないという点にある」と話す。鄒平県に隣接するズー博市に暮らす陳浩さん(41)は、「ケンタッキーはそれほどヘルシーだと思わない。時間がないときしか利用しない」という。
マクドナルドとケンタッキーは大都市で提供する商品とサービスの調整を進めている。マクドナルドは中国のほぼ全店舗を改装し、トレンド感のある店作りを進め、カフェコーナーも併設した。先月にはヤム・ブランズ中国法人が運営するレストランKPROが東部都市の杭州にオープンした。サラダ、サンドイッチ、フレッシュジュース、コーヒー、クラフトビールなどを提供し、ケンタッキーとの唯一の共通点はフライドチキンを提供することだ。また科学技術製品に対して目の肥えた大都市の専門家たちを呼び込むため、KPROはインターネット大手・阿里巴巴(アリババ)が設計した顔認証決済システムを導入した。
報道によると、こうしたバージョンアップ戦略はケンタッキーには有効だ。過去4年間の営業収入の減少・足踏みの時期を経て、今年6月30日から8月31日までの3カ月間には、ケンタッキーの店舗での売上高は前年同期比7%増加した。(編集KS)